今回紹介するのは、一般的な出版流通を通らず、ごく一部で知られるようになった異色の一冊、『創作』です。
この本は、もともとある古物商が古道具屋のワゴンセールで偶然見つけた、一冊の一般人の日記に由来しています。
内容は、1973年から1975年までの2年間にわたる、無名の若者の生活と内面を記録したもの。
正式な書籍ではなく、ISBNも付与されていません。発見者の手で体裁が整えられ、現在の形となりました。
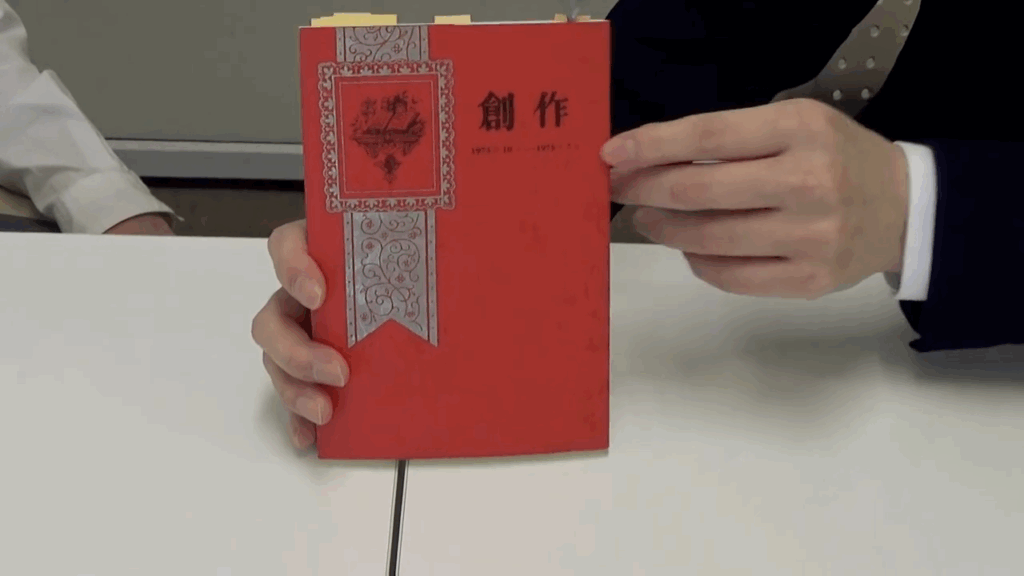
本の出自──「拾われた日記」
この日記は、元々は誰にも見せるつもりがなかったプライベートな記録です。
発見した古物商によって「創作」というタイトルが与えられ、整えられました。
そのため、商品として意図されたものではなく、一個人の私的な営みが、偶然によって表に出たものです。
装丁はシンプルで上品ですが、正式な出版社のロゴやコードもなく、流通も極めて限定的です。
何が書かれているのか
内容は一言でいえば、「作家志望の若者が、自堕落な生活に苦しみながら、それでも何かを書こうとし続ける記録」です。
- 読んだ本のタイトル
- 自己嫌悪
- パチンコや麻雀に費やした日々
- 酒に逃げる夜
- 「このままではいけない」と悔いる朝
この繰り返しが、赤裸々に、淡々と綴られています。
誰に見せるわけでもないため、取り繕いも演出もありません。
実際の記述から
たとえば、こんな風に書かれています。
「1月13日、10時30分頃きくさんが来る。きくさんとパチンコ、3時まで。家にいても退屈である。」
「11時15分現在、酒を飲んでいる。私は人が何かを感じる小説を書きたい。小説家と言われるところの人間にでもなりたいと思う。」
「もちろん思うだけで努力などしてはいないが。」
翌日にはこう続きます。
「麻雀5000円負け」
このどうしようもなさ、生活のリアルさがこの日記の最大の特徴です。
呪われた「創作」という営み
本書を読んで感じるのは、何かを作ろうとする者が背負う宿命のようなものです。
書き始めたものの、現実に流され、負け、自分を呪い、また再起を誓う。
それでも、また堕ちる。
作品を完成させることもなく、しかしやめることもできない。
「創作」とは、彼にとって祝福ではなく、呪いのような営みであったことが伝わってきます。
最後は唐突に終わる
1975年7月26日の記述を最後に、日記は突然終わります。
「母が今夜2時から釣りにいくそうだ。親父はこちらの部屋で寝る。」
あまりにあっけない結び。
そこにドラマチックな幕引きも、文学的な美しさもありません。
まるで、何気ない日常の延長線上で、自然に筆が置かれたかのようです。
『創作』を読む意味
この『創作』は、いわゆる完成された文学作品ではありません。
しかし、それゆえに読む者に強い衝撃を与えます。
- 誰にも読まれない前提で書かれた文章
- 作り手としての苦悩と自堕落
- ありのままの葛藤
創作に関わるすべての人にとって、「なぜ書くのか」「なぜ続けるのか」という問いを突きつけてきます。
完成された小説や、成功者の自伝では絶対に味わえない、**生々しい「創作の現場」**がここにはあります。
まとめ
『創作』は、名もない一人の若者の自己記録でありながら、
創作するとは何か、生きるとは何かを静かに、しかし確実に語りかけてきます。
決して誰にでも薦められる本ではありませんが、
「作る」という営みに苦しみ続けた誰かの叫びに、そっと耳を傾けたい人には、忘れがたい読書体験となるでしょう。
YouTubeでも紹介しています

